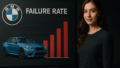BMWのデザインに対して「ひどい」と感じて検索にたどり着いた方は少なくないかもしれません。特に最近では、キドニーグリルの巨大化や「豚鼻」と揶揄される縦長のフロントデザインに対し、「ダサい」といった声が国内外で多く見られるようになりました。
こうした評価の背景には、デザインの迷走とも取れる急激な方向転換や、現在のデザイナーがどのような意図で手がけているのかといった要素が関係しています。
また、「なぜBMWは豚鼻デザインを続けるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。かつてのスマートで端正な印象と比べると、今のBMWはどこか違和感を覚えるという意見が出るのも無理はありません。一方で、グリルがかっこいいと感じる層や、海外の反応では評価されているという視点もあります。
本記事では、BMWのデザインがなぜ「ひどい」と言われるのかを多角的に検証し、巨大化したキドニーグリルや3色カラーの採用、日本人デザイナーの関与などにも触れながら、賛否の理由と今後の展望について考察していきます。
- キドニーグリルの巨大化や豚鼻デザインが批判される理由
- BMWのデザイン変更が市場戦略とどう関係しているか
- 現在のBMWデザインに対する国内外の反応や評価
- デザイナーやブランド戦略がデザインに与える影響
BMW デザイン:ひどいと感じる理由を探る

- キドニーグリルの巨大化はダサいのか?
- 最近のBMW豚鼻デザインは本当にダサい?
- デザインが迷走していると言われる背景
- BMWグリルの3色カラーはなぜダサい?
- BMWが豚鼻デザインを続ける理由とは
キドニーグリルの巨大化はダサいのか?
キドニーグリルの巨大化については、「ダサい」と感じるかどうかは個人の感性によって異なるものの、近年のBMWに対する批判の中で非常に目立つポイントとなっています。確かに、かつてのBMWが持っていた洗練された印象や控えめな高級感に惹かれていた層からは、「バランスが崩れた」「威圧感が強すぎる」といった声が多く上がっています。
このような評価が出てきた背景には、グリルのサイズだけでなく、それが車全体のデザインに与える影響があります。従来のキドニーグリルは、車体のデザインの一部として自然に溶け込んでおり、ブランドアイデンティティを感じさせつつも主張しすぎない絶妙な存在感を放っていました。しかし近年では、特に一部のSUVモデルやスポーツモデルで、グリルが過度に拡大されており、「目立たせること」自体が目的となっているように映るデザインも見られます。
例えばBMW 7シリーズやX7などでは、グリルがフロントマスクの中心を完全に支配している印象を受けるため、これまでのBMWらしさを期待していたファンほど違和感を覚えることが多いようです。その結果、「BMWらしい高級感よりも、自己主張の強さが前面に出てしまった」との評価が広がっています。
一方で、中国市場やアメリカ市場など、大型グリルが好まれる地域にとってはこの変更が歓迎されている面もあります。つまり、BMWは特定市場のニーズを重視した結果として、グローバル全体での評価が割れてしまっているのです。
いずれにしても、キドニーグリルの巨大化にはマーケティング的な意図や戦略があると考えられますが、それが万人受けするかどうかは別の問題です。結果として、「ダサい」と受け取られる理由は、ブランドイメージと視覚的バランスのギャップにあるといえるでしょう。
最近のBMW豚鼻デザインは本当にダサい?

BMWの「豚鼻デザイン」とは、キドニーグリルが縦に大きく引き伸ばされたことで、フロント部分がまるで豚の鼻のように見えるという意見からつけられた俗称です。特に近年では、このデザインに対して「ダサい」という批判が一部のファンやネットユーザーの間で広がっていますが、実際にはデザイン意図を理解することで異なる見方も可能になります。
この「豚鼻」デザインは、BMWがブランドの個性を強調するために意図的に採用しているものです。これには、視覚的インパクトを通じて競合との差別化を図る狙いがあるとされます。特にBMW M4やiXなど、最新モデルではグリル部分が縦長に伸びることで、よりスポーティかつ未来的な印象を与えるデザインが採用されています。
とはいえ、長年BMWを支持してきたユーザーからすると、「あまりにも従来のイメージからかけ離れている」「高級車としての品格に欠ける」といった否定的な意見が出るのも無理はありません。こうした声が「ダサい」という評価につながっているのです。これは、単に美的な好みの問題ではなく、ブランドに対する期待や愛着が裏切られたという感情に起因しています。
一方で、BMW側としてはこのような反応も織り込み済みであり、「強い印象を残すデザインこそが現代のラグジュアリーブランドに必要だ」との信念のもと、あえて挑戦的なデザインを貫いている側面があります。
つまり、豚鼻デザインが本当にダサいかどうかは一概には言えません。それはBMWのデザイン戦略の一環であり、見る人の価値観や期待によって大きく評価が分かれるポイントなのです。
デザインが迷走していると言われる背景
BMWのデザインが「迷走している」と言われるようになった背景には、近年の急激な変化とその方向性に対する賛否両論が深く関係しています。特に長年BMWを愛用してきたファンや、過去のデザインを高く評価していた層にとっては、現行モデルのスタイルが「一貫性を失っている」「ブレている」と感じられることが少なくありません。
このように感じさせる要因の一つは、モデルごとのデザイン言語に統一感がなくなっている点です。かつてのBMWは、どの車種を見ても「BMWらしい」と思える共通のフォルムやフロントデザインがありました。しかし最近では、モデルによってグリルの形やヘッドライトの配置、さらにはリアの処理までが大きく異なっており、「同じブランドの車とは思えない」といった意見も散見されます。
また、エレガントさや端正さを重視していた過去の路線から、よりアグレッシブで大胆な造形へと大きく舵を切ったことも、違和感を生む一因です。これにより、従来のユーザーが求めていたクラシカルな高級感が損なわれてしまったと感じる人も多いのです。
一方で、EV(電気自動車)やSUVといった新たな市場に対応するため、BMWとしてもデザインを刷新する必要に迫られているのは事実です。技術的な進化や安全基準の変化に伴い、ボディ形状やフロント構造に一定の制限があることも無視できません。
このように考えると、デザインの迷走とは単なる失敗ではなく、「ブランドらしさを維持しながらも、変化に対応しなければならない」という葛藤の現れとも言えます。だからこそ、迷走と評価される一方で、それを挑戦と捉える声も存在しているのです。
BMWグリルの3色カラーはなぜダサい?

BMWのグリルに配される「3色カラー」が「ダサい」と言われることがありますが、この評価にはいくつかの背景があります。まず知っておきたいのは、この3色は単なる装飾ではなく、BMWのMシリーズにルーツを持つ由緒あるカラーリングであるという点です。赤・青・水色の3色は、それぞれモータースポーツ、BMWの伝統、そしてパートナー企業を表す意味合いがあります。
しかし、意味があるからといって、すべての人がそれを魅力的に感じるわけではありません。実際に「ダサい」と感じられるのは、この3色がグリル部分に後付けのように取り付けられていることに起因していると考えられます。カラーの配置や素材感が本体デザインと調和していないと、いくら歴史ある色であっても、全体の完成度を損ねてしまうのです。
また、3色カラーの使い方が限定的であることも問題視されています。例えば、純正パーツではなくアクセサリーパーツや社外品として販売されることが多いため、品質や見た目にばらつきが出やすく、結果的にチープな印象を与えてしまうケースもあります。このような視点から、「せっかくの高級車なのに、まるで安価なドレスアップパーツのように見える」と受け取られてしまうのです。
さらに、日本国内ではカラフルな装飾に対して「派手すぎる」「悪目立ちする」といった否定的な文化的傾向もあり、それが「ダサい」という評価に拍車をかけている面もあります。控えめな美意識を持つ人が多い中で、あの鮮やかな配色は、どうしても浮いてしまうのです。
このように、「3色カラーがダサい」と感じられるのは、デザインの配置バランス、文化的な感覚、さらには取り付け方法の問題など、複数の要因が重なっているといえます。伝統的な意味を知った上で選ぶかどうかは、ドライバー自身の美意識に委ねられる部分でもあります。
BMWが豚鼻デザインを続ける理由とは
BMWがあえて「豚鼻」と揶揄されるようなデザインを続けている背景には、単なる見た目の好みを超えた、戦略的な判断が存在しています。このデザインは一部のユーザーから否定的な声が上がっているものの、同時にブランドアイデンティティの強化という面では一定の成果を上げているのです。
特に、現代の自動車市場では車の性能だけでなく、ひと目でそのブランドと分かる「顔」のデザインが重要視されています。各メーカーが個性を競い合う中で、BMWは「豚鼻」と形容される大胆なキドニーグリルの拡大によって、他社とは一線を画す存在感を確立しようとしているのです。
また、成長著しい中国やアメリカといった海外市場では、デザインに対してより派手さやインパクトを求める傾向があります。実際、これらの市場では大型グリルのデザインが高く評価されており、BMWとしてもそうした消費者の志向を無視することはできません。つまり、国内外の評価のズレが、このデザインが継続される一因になっているのです。
さらに、BMWは単にグリルを大きくするだけでなく、冷却効率やエアロダイナミクスといった機能面での設計変更も並行して行っています。デザイン変更が見た目だけの話ではないことも、同社がこの路線を維持する理由の一つといえるでしょう。
それでも「なぜあのデザインなのか」と疑問を持つ声は少なくありませんが、BMWにとっては、あの形状こそが新たな時代の象徴であり、競争激化する市場でブランドの存在感を強調するための“武器”でもあるのです。
こうした観点から考えると、豚鼻デザインは一見して奇抜に映るかもしれませんが、それが継続されるのは、企業としての意志とグローバル戦略に基づいた選択であると理解できるはずです。
BMW デザイン:ひどいの評価を見直す視点

- 現在のデザイナーに日本人はいるのか?
- キドニーグリルはかっこいいという声も
- BMWグリルに対する海外の反応は?
- デザインはブランド戦略の一部なのか
- 過去のBMWと比較して見える変化とは
- 賛否両論が生まれる理由と今後の展望
現在のデザイナーに日本人はいるのか?
BMWのデザインチームに日本人が在籍しているのかどうかについては、近年注目を集める話題となっています。実際には、BMWグループ内で活躍している日本人デザイナーは存在しており、かつてはエクステリアやインテリアの一部プロジェクトを担当した実績もあります。
例えば、過去にBMW i部門で活躍したデザイナー・和田智(わださとし)氏は、日本人としてBMWに大きな影響を与えた人物の一人です。和田氏はBMW Z4の初代モデルのデザインを手がけたことでも知られており、国際的にも評価が高いデザイナーです。ただし現在、BMWのデザイン部門で直接チーフポジションを務める日本人は、表立った存在としては確認されていません。
一方で、グローバル企業であるBMWは、多国籍の才能を積極的に起用しているため、プロジェクト単位や外部パートナーとして日本人が関わることは十分に考えられます。特に、デジタル領域やコンセプトカー開発では、外部からのコラボレーションが盛んに行われており、その中には日本人の名前が挙がることもあります。
このように、正式なチーフデザイナーとしての日本人の登用は現在のところ確認されていないものの、BMWの開発現場では間接的にでも日本人デザイナーの感性が関与している可能性は否定できません。それは、BMWが世界中の市場に対応したデザインを生み出す中で、アジア市場の視点も取り入れようとしている証拠ともいえるでしょう。
キドニーグリルはかっこいいという声も

BMWの象徴ともいえる「キドニーグリル」には、「かっこいい」と評価する声も少なくありません。デザイン面で賛否が分かれる要素ではありますが、好意的な意見にも十分な説得力があります。
まず、グリルの二分割デザインは、1930年代から受け継がれるBMWの伝統であり、他の自動車ブランドには見られない個性的な特徴です。この伝統を現代風にアレンジしたデザインは、視覚的にブランドの一貫性を保ちつつ、未来的な印象を与えることに成功しています。特に新型モデルでは、LEDライトやセンサーが組み込まれることで、技術的な進化もアピールできる仕様になっています。
また、大きくデザインされたキドニーグリルは、迫力や高級感を演出するうえでも効果的です。実際、多くのオーナーやファンからは「フロントフェイスの存在感が圧倒的」「夜間に見ると一層引き締まって見える」などのポジティブな感想が寄せられています。SUVや大型セダンなど、重厚なボディとの相性も良く、全体としてのバランスを評価する声も根強いです。
さらに、欧州やアメリカ市場を中心に、グリルの大型化が“ステータスシンボル”として受け入れられている現実もあります。競合他社もフロントデザインに力を入れる中で、BMWのグリルはそのままブランド力の象徴となっているのです。
このように見ていくと、キドニーグリルを「かっこいい」と評価する人々にとっては、単なるデザインではなく、BMWというブランドの世界観や美学に共鳴している側面が大きいと考えられます。
BMWグリルに対する海外の反応は?
BMWのグリルデザイン、とりわけ大型化されたキドニーグリルに対する海外の反応は、国や文化によって大きく異なります。評価が二極化している点は日本と共通していますが、海外特有の受け止め方も多く見られます。
アメリカでは、グリルの大きさが「堂々としていて迫力がある」「高級車らしいインパクトがある」として、比較的好意的に受け入れられている傾向にあります。特にSUV市場が強い北米では、力強さや存在感を重視するユーザーが多く、BMWの新型グリルもそうしたニーズに合致していると見られています。
一方、ヨーロッパではBMWの本拠地であるドイツを含めて、やや厳しい目が向けられている場面もあります。伝統を重んじる文化や、ミニマルなデザインを好む傾向が強いため、「やりすぎ」「旧モデルの方が美しい」といった声も一定数存在しています。ただし、すべての層が否定的というわけではなく、モデルやグレードによっては「先進的」「未来志向で良い」と評価されることも少なくありません。
中国市場においては、大型グリルがステータスや威厳の象徴として非常に好まれる傾向にあります。そのため、BMWがあえてグリルを拡大しているのは、中国市場での競争力を高めるための戦略の一環とも言えるでしょう。都市部ではブランドへの信頼感やデザインの派手さが選択の重要な基準になるため、視覚的なインパクトはむしろ歓迎されるポイントとなります。
このように、BMWグリルに対する海外の反応は、文化的価値観や市場の志向によってさまざまです。世界中のユーザーの反応を踏まえて、BMWがどのようなデザイン戦略を取っていくのかは、今後の注目点と言えるでしょう。
デザインはブランド戦略の一部なのか

自動車のデザインは単なる見た目の良し悪しにとどまらず、企業のブランド戦略において非常に重要な役割を果たしています。特にBMWのようなプレミアムブランドにおいては、デザインがブランドの個性や哲学を視覚的に表現する手段として機能しています。
BMWは長年にわたって「駆けぬける歓び(Sheer Driving Pleasure)」というコンセプトを掲げてきました。デザインにおいても、この理念を反映させるために、スポーティさや洗練された印象を重視しています。こうした価値観をデザインに落とし込むことで、ブランド全体のイメージを強化し、他社との差別化を図っているのです。
また、グリルやライト形状、ボディのラインなど、BMWならではのデザイン要素は、消費者が一目で「BMWだ」とわかるよう意図されています。これは、製品を通じてブランドの世界観を共有するための戦略であり、企業イメージの維持・向上に直結するものです。
このように、自動車のデザインは製品の外見を超えて、ブランドの方向性やマーケティング戦略と深く結びついています。だからこそ、デザインに対する世間の評価が企業にとって重要な指標となり、特に注目される要素となるのです。
過去のBMWと比較して見える変化とは
これまでのBMWと現在のBMWを比較すると、デザインにおける方向性の変化が明確に見えてきます。特にフロントマスクの印象は、過去とは大きく異なってきており、長年のファンからもさまざまな声が上がっています。
例えば、2000年代初頭のBMWは、均整の取れたグリルと流麗なライン、控えめで上品なフロントフェイスが特徴でした。車種によって違いはあるものの、どのモデルも共通して「スマートでスポーティ」というイメージが強く、控えめながら存在感を放つデザインが多く見られました。
一方、現在のモデルでは、グリルの大型化やライト形状の鋭利化、ボディ全体の輪郭の強調といったデザイン要素が目立つようになっています。特に「豚鼻」と揶揄される巨大なキドニーグリルは、象徴的な変化の一つです。これは一部のユーザーにとっては攻撃的で違和感があるものと映り、従来の「控えめな美しさ」とは方向性が異なって見えることもあります。
ただし、変化の背景にはグローバル市場における競争や、電動化・自動運転といったテクノロジーとの融合も大きく関係しています。つまり、デザインの変化は単なる見た目の刷新ではなく、BMWが次の時代を見据えて新たな価値観を提案している証でもあるのです。
賛否両論が生まれる理由と今後の展望

BMWのデザインに対して賛否が分かれるのは、複数の要素が絡み合っているからです。単純に「好き」「嫌い」という感情的な反応にとどまらず、ブランドの歴史やユーザーの価値観の変化、さらには時代背景までが影響しています。
一つには、BMWが長年築いてきた伝統と、現在のモダンなデザインのギャップが挙げられます。長くBMWを支持してきた層にとっては、「クラシックな佇まい」こそがブランドの魅力であり、それが失われたように感じることが反発につながっています。一方で、新しい顧客層に向けては、「インパクト」や「独自性」を前面に打ち出したデザインが求められており、実際に新興市場では高評価を得ているケースもあります。
さらに、SNSなどの拡散力が強まった現代では、デザインの変化が瞬時に話題となり、感情的な意見が飛び交いやすい環境が整っています。その結果として、評価が極端に二極化しやすい傾向があります。
では今後、BMWはどういったデザイン戦略を採るのでしょうか。現在の流れを見る限り、ブランドのアイデンティティは保ちつつも、より先鋭的でグローバルな嗜好に対応したスタイルを打ち出し続ける可能性が高いと考えられます。特に電動車両(EV)ラインナップの拡充に合わせて、より未来志向のデザインへとシフトする動きはすでに進行中です。
このように、賛否が分かれるのは、BMWがブランドの進化を模索する中で避けて通れない道でもあります。変化をどう受け止め、どのような顧客と共に歩んでいくかが、今後のBMWデザインの鍵となるでしょう。
BMW デザイン:ひどいと言われる理由を総括
BMWのデザインがひどいと感じられる理由は、キドニーグリルの巨大化や伝統からの乖離、モデル間の統一感の欠如など多岐にわたります。従来のファンとのギャップが、批判を生む要因となっています。
記事のポイントをまとめます。
- キドニーグリルの巨大化が視覚的バランスを崩している
- 従来の洗練された高級感が薄れている
- 一部モデルでデザインの統一感が欠けている
- フロントマスクが威圧的すぎると感じる層がいる
- 伝統的なイメージとのギャップが違和感を生んでいる
- 「豚鼻」と揶揄されるグリル形状に抵抗を感じるユーザーがいる
- ブランドの方向性が視覚的に不明瞭になっている
- 従来のBMWファンの期待に応えきれていない
- 3色グリル装飾が車体デザインと調和していない
- 後付け風のグリルカラーがチープに映る場合がある
- モデルによって評価のばらつきが大きい
- 海外市場向けデザインが日本市場で受け入れにくい
- デザイン変更が機能面と結びついているケースがある
- 批判の背景に文化的な美意識の違いがある
- SNSによる拡散でデザインへの否定的評価が増幅されている