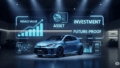日本の技術の結晶として世界に誇る日産GT-R。その次期モデルとして注目されるGT-R R36のデザインをめぐり、「ダサい」という手厳しい声も上がっています。
現行のR35が長い歴史に幕を下ろし、一時は開発中止の噂まで流れたことで、多くのファンがその先の情報を心待ちにしていることでしょう。
この記事では、GT-R R36は本当にいつ発売されるのか、気になる新車価格や値段はどうなるのかといった最新情報をお届けします。また、長年ファンを魅了してきたGT-R 人気な理由はどこにあるのか、そして指摘されがちなGT-R 欠点まで、多角的に掘り下げていきます。
さらに、ライバルであるNSXやレクサスLFAと比べて一体どっちが速いのか、その驚異的な性能にも迫ります。噂の真相とGT-Rの未来を、ぜひご覧ください。
- 「ダサい」と評されるデザインの意図と伝統継承
- 開発中止の噂の真相と発売時期の予測
- 1000馬力超の性能と2000万円超の価格
- GT-Rブランドが持つ歴史と人気の背景
GT-R R36はダサい?デザインの評価とコンセプト

- コンセプトカーから見る未来のデザイン
- 歴代R35から継承されるデザイン要素
- GT-Rが持つ伝統と人気の理由
- 視界が悪い?指摘されるGT-Rの欠点
- 丸目テールはR36でも継承されるか
コンセプトカーから見る未来のデザイン
次期GT-Rのデザインを占う上で、最も重要な存在がコンセプトカー「ニッサン ハイパーフォース」です。このモデルは、2023年のジャパンモビリティショーで公開され、多くの自動車ファンの注目を集めました。言ってしまえば、これは日産が描く未来の高性能スポーツカーの姿そのものであり、R36の開発の方向性を示す道しるべと言えるでしょう。
「ハイパーフォース」のデザインは、これまでのGT-Rとは一線を画す、極めて先進的なものです。全体のフォルムは、空力性能を最大限に高めることを目的に設計されており、NISMOレーシングチームと共同開発されました。例えば、フロントボンネット下の二段構造や、車体後方の二重構造ディフューザーは、強力なダウンフォースを発生させ、高速走行時の安定性を向上させるための専用装備です。
また、軽量かつ高強度なカーボン素材をボディの随所に使用し、ホイールにも空力とブレーキ冷却性能を高めるための工夫が凝らされています。このように、エクステリアの各パーツは見た目のインパクトだけでなく、すべてが走行パフォーマンスの向上という機能に直結しているのです。
もちろん、完全に新しいデザインの中にも、GT-RとしてのDNAは感じられます。フロントマスクの形状や全体のシルエットには、歴代モデルの面影が巧みに織り交ぜられており、長年のファンであれば思わずニヤリとしてしまうかもしれません。このコンセプトカーが、市販車となったときにどこまで忠実に再現されるのか、非常に楽しみです。
| 「ハイパーフォース」の注目デザイン | 期待される効果・目的 |
|---|---|
| NISMOと共同開発の空力設計 | 強力なダウンフォースと冷却性能の両立 |
| 二重構造ディフューザー | 車体全体の空気の流れを最適化 |
| プラズマアクチュエーター | コーナリング時のグリップ力を最大化 |
| カーボン製のボディとホイール | 車体の軽量化と高剛性の実現 |
| 再解釈されたテールランプ | GT-Rの伝統継承と未来感の演出 |
歴代R35から継承されるデザイン要素

新型GT-Rは革新的なクルマになることが予想されますが、その一方で、18年という長い歴史を持つR35型から受け継がれるデザイン要素も間違いなく存在するでしょう。R35は2007年の発売以来、一度もフルモデルチェンジを行わず、毎年のように改良を重ねてきました。この熟成の過程で築き上げられたデザイン哲学は、次期モデルの基盤となるはずです。
そのことを象徴するのが、R35の2024年モデルです。このモデルではフロントバンパーのデザインが変更され、往年のスカイラインGT-R、特にR34型を彷彿とさせるスタイルが採用されました。この変更は多くのファンから高く評価されており、日産がいかに過去のヘリテージを大切にしているかの証明と言えます。
そして、GT-Rのデザインを語る上で絶対に欠かせないのが、伝統の「丸型4灯テールライト」です。これはR32型から続くGT-Rの象徴であり、多くのユーザーがGT-Rらしさを感じる部分です。
前述のコンセプトカー「ハイパーフォース」においても、完全な円形ではないものの、この丸目テールを再解釈した先進的なデザインが採用されていました。このことから、R36でも何らかの形でこのアイコニックなデザインは継承される可能性が非常に高いと考えられます。
R35が長年愛された理由の一つに、迫力あるワイドなボディや機能美を感じさせるインテリアデザインがあります。次期モデルでは、これらの要素が未来的な空力デザインとどのように融合し、新たなGT-R像を創り出すのかが、大きな注目点となります。
GT-Rが持つ伝統と人気の理由
GT-Rがなぜこれほどまでに国内外で絶大な人気を誇るのか。その理由は、単に車両の性能が高いからというだけではありません。その背景には、レースシーンで刻んできた輝かしい歴史と、他のスーパーカーとは一線を画す独自のコンセプトが存在します。
古くからGT-Rはレースで勝つために生まれてきたクルマでした。初代モデル「スカイラインGT-R(通称ハコスカ)」は、当時のツーリングカーレースで圧倒的な強さを見せ、「羊の皮を被った狼」という伝説を築きました。その後、R32型はSUPER GTの前身となるレースで無敗神話を打ち立て、GT-Rの名を不動のものにしたのです。
近年では、映画「ワイルド・スピード」シリーズやレースゲームに登場したことで、特にアメリカをはじめとする海外での知名度が飛躍的に向上しました。R34のかっこよさに憧れ、日本車ファンになったという方も少なくないでしょう。
そして、R35の登場はGT-Rの歴史に新たな1ページを加えました。R35が掲げたのは「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」という「マルチパフォーマンス・スーパーカー」の概念です。
300km/hを超える高速走行性能を持ちながら、大人4人が乗れる室内空間と日常使いできる快適性を両立。この懐の深さが、従来のスポーツカーファンだけでなく、新たなユーザー層をも獲得したのです。
加えて、VR38DETTエンジンを「匠」と呼ばれる熟練の職人が一台一台手作業で組み立てるという特別な生産方式も、所有する満足感を高める大きな要因となっています。このような物語性や伝統があるからこそ、GT-Rは単なる工業製品を超えた存在として、世界中の人々を魅了し続けているのです。
視界が悪い?指摘されるGT-Rの欠点

NISSAN GT-Rは、世界トップクラスの走行性能を誇るスーパーカーですが、その卓越したパフォーマンスと引き換えに、いくつかの欠点も指摘されています。その中でも特に有名なのが、運転時の「視界の悪さ」です。これは主に、パフォーマンスを最優先した結果のデザインに起因します。
GT-Rのクーペボディは、高い剛性を確保するためにAピラーやCピラーが太く設計されています。また、ドライバーをしっかりと包み込むようなコクピットデザインは、サイドウィンドウの下端が高い位置にくるため、運転席に座ると「バスタブに首まで浸かったような感覚」と表現されることもあります。
このため、特に左折時や駐車の際に助手席側の死角が大きくなりがちで、ボディ側方の低い位置にある縁石などの障害物を発見しにくいというデメリットがあります。全幅が1900mmに迫るワイドな車体と、最小回転半径の大きさも相まって、街中の狭い道や駐車場では、運転に細心の注意が必要となるでしょう。
もちろん、これはGT-Rがサーキットなどでの高速走行を前提に、安全性とパフォーマンスを追求した結果です。しかし、次期モデルであるR36では、この長年の課題がどのように改善されるのか注目が集まります。
最新のデジタル技術、例えば高精細なカメラを使った360°セーフティアシスト(アラウンドビューモニター)やセンサー類が標準装備されれば、デザインの魅力はそのままに、運転のしやすさが飛躍的に向上する可能性があります。
| GT-R(R35)で指摘される主な欠点 | 次期モデル(R36)で期待される改善策 |
|---|---|
| 側方・後方の視界の悪さ | 高性能カメラやセンサーによる視界支援システムの搭載 |
| ワイドな車幅による取り回しの難しさ | 360°セーフティアシストによる駐車・幅寄せ支援の強化 |
| 初期モデルのトランスミッションの変速ショック | 電動化技術によるシームレスで滑らかな変速の実現 |
| 部品供給の懸念と維持費の高さ | 新世代プラットフォーム採用による部品の共通化と信頼性向上 |
丸目テールはR36でも継承されるか
GT-Rのデザインを語る上で、ファンの間で最も注目される要素の一つが、伝統の「丸目4灯テールライト」でしょう。結論から言えば、次期モデルR36においても、この象徴的なデザインは何らかの形で継承される可能性が極めて高いと考えられます。
その理由は、この丸目テールが単なるデザインの一部ではなく、GT-Rというブランドの魂そのものだからです。この伝統は、1989年に登場したスカイラインGT-R(R32)から始まり、R33、R34、そしてR35に至るまで、世代を超えて一貫して受け継がれてきました。夜間、後方からテールライトを見ただけで、誰もが「GT-Rだ」と認識できるほどの強力なアイデンティティとなっています。
日産自身もこの伝統の価値を深く理解しています。事実、R35の最終モデルのプロモーションでは、過去のモデルのカタログをオマージュした写真が公開されるなど、歴史やファンを大切にする姿勢が見られました。
そして何より、R36のデザインの方向性を示唆するコンセプトカー「ニッサン ハイパーフォース」に、その答えがあります。
このモデルのリアデザインを見ると、完全な円形ではないものの、円をモチーフにした複数のLEDグラフィックで「丸目4灯」が見事に再解釈・表現されています。これは、伝統をリスペクトしつつ、EV時代にふさわしい先進的なデザインへと進化させようという、日産の明確な意思表示と言えるでしょう。
このように考えると、R36のテールライトは、形こそ変わるかもしれませんが、「丸目4灯」というGT-Rの魂は、間違いなく次世代へと受け継がれていくはずです。
GT-R R36がダサいとの噂を覆す最新情報

- 開発中止は誤解?日産の公式見解
- 次期GT-R R36はいつ発売される?
- R36の最新情報!電動化で1000馬力超か
- 新車価格は1500万円超?R36の値段
- GT-RはNSXやLFAより速い?
- 伝統と革新、R36への期待
開発中止は誤解?日産の公式見解
「GT-R R36の開発は中止された」という噂が広まり、多くのファンがその動向を固唾をのんで見守っています。しかし、この情報は正確ではありません。結論から言うと、開発中止は誤解であり、日産は次世代のGT-Rを諦めてはいないのです。
この噂が広まった大きなきっかけは、R35型GT-Rが2025年8月をもって生産を終了すると正式に発表されたことにあります。18年という長きにわたる歴史に幕を下ろすというニュースは、多くの人に「GT-Rブランドそのものが終わるのではないか」という印象を与えました。
生産終了の理由は、年々厳しくなる騒音規制や安全基準への対応、そして一部部品の調達が困難になったことが挙げられています。これはあくまで現行モデルの生産継続が難しくなったという事実であり、次期モデルの開発を否定するものではありません。
実際、日産の幹部は「GT-Rは日産にとって非常に重要なモデルであり、あらゆる可能性を探っている」と公に発言しています。さらに、2023年のジャパンモビリティショーで、次期GT-Rを強く示唆するコンセプトカー「ニッサン ハイパーフォース」を大々的に展示したことこそ、開発が水面下で継続している何よりの証拠と言えるでしょう。
メーカーがこれほど注目度の高いコンセプトカーを公開するのは、その先にある市販化を見据えているからに他なりません。
| 巷の噂・憶測 | 日産の公式な姿勢・事実 |
|---|---|
| R35の生産終了をもって開発は中止された | 部品調達難等でR35の生産は終了したが、開発中止は否定 |
| 電動化の波でGT-Rはもう出ない | 幹部が次世代モデルの検討を明言。電動化を前提に開発中 |
| 具体的な情報がないため計画は白紙になった | コンセプトカー「ハイパーフォース」で未来像を具体的に提示 |
| 経営状況的に開発は困難ではないか | GT-Rは日産のブランドを象徴する重要なモデルと位置付け |
次期GT-R R36はいつ発売される?
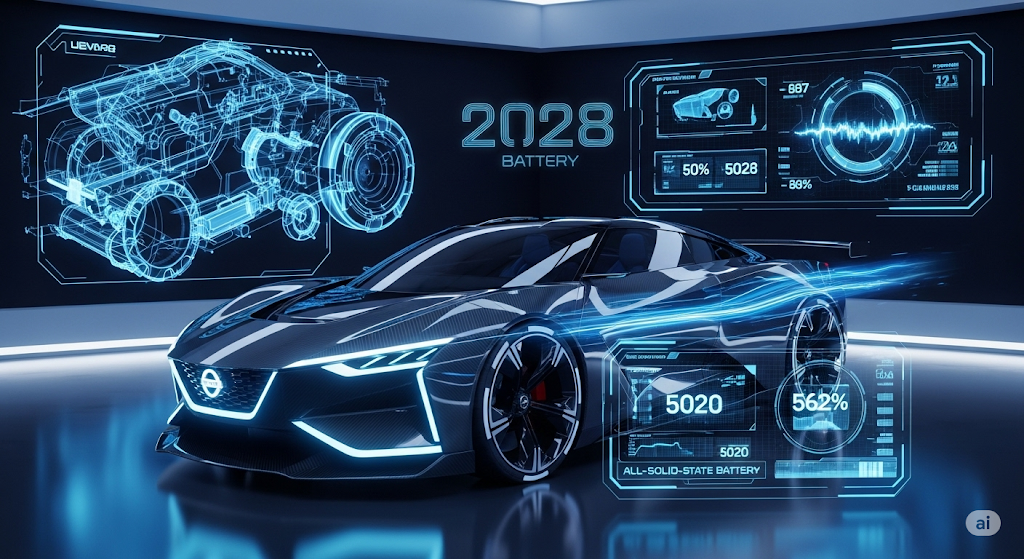
開発が継続されているとなると、次に気になるのは「一体いつ発売されるのか」という点です。現時点で日産から正式な発売日は発表されていませんが、多くの情報や専門家の見解を総合すると、2028年頃が一つの有力なターゲットイヤーとして浮上しています。
R35型が2025年8月に生産を終えた後、すぐさま新型が登場するわけではありません。高性能なスーパーカーの開発には、設計からテスト、生産ラインの準備まで、通常数年の期間を要します。そう考えると、2~3年の準備期間を設けた2028年というスケジュールは、非常に現実味のあるタイミングです。
そして、この2028年という時期を裏付けるもう一つの重要な要素が、日産の技術ロードマップです。日産は、次世代バッテリーとして期待される「全固体電池」を2028年頃に実用化することを目指しています。この全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、小型軽量化や急速充電にも有利なため、次世代の高性能EVには不可欠な技術とされています。
この革新的なバッテリーを、ブランドの象Cである次期GT-Rに初搭載する、というシナリオは十分に考えられます。最高の技術を最高のクルマに投入するという意味でも、全固体電池の実用化とR36のデビューは、同じタイミングで行われる可能性が高いのです。もちろん、これは現時点での予測であり、今後の開発の進捗次第ではスケジュールが前後する可能性もあります。
R36の最新情報!電動化で1000馬力超か
次期モデルR36の最大のトピックは、そのパワートレインにあります。長年親しまれてきた純粋なガソリンエンジンから、モーターを組み合わせた電動モデルへと生まれ変わることは、ほぼ確実視されています。そして、そのスペックは私たちの想像を絶するレベルに達するかもしれません。
注目すべきは、コンセプトカー「ニッサン ハイパーフォース」が示した性能です。このモデルは、全固体電池と高出力モーターを組み合わせ、最大出力1,000kW、つまり約1360馬力というとてつもないパワーを発生するとされています。これは現行のGT-R NISMO(600馬力)の2倍以上であり、世界のあらゆるスーパーカーと比較してもトップクラスの数値です。
この圧倒的なパワーを路面に伝えるため、駆動方式には日産が誇る電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の進化版が採用されると見られています。前後2つのモーターを緻密に制御し、どのような路面状況でも最適な駆動力を配分することで、異次元の加速性能とコーナリング性能を実現します。0-100km/h加速タイムは、現行モデルを大幅に上回り、2秒台前半に達する可能性も十分にあります。
パワートレインの具体的な形式については、全固体電池を搭載したピュアEV(電気自動車)になるという見方が有力ですが、一部では既存のVR38DETTエンジンをベースにした高性能ハイブリッドになるという声もあります。いずれにしても、GT-Rが電動化によってパフォーマンスをさらに向上させ、新たな時代のスーパーカーとして君臨することに期待が高まります。
新車価格は1500万円超?R36の値段

次期GT-R R36の車両価格は、多くのファンが最も気にする情報の一つでしょう。まだ日産からの正式な発表はありませんが、搭載される技術やR35の最終価格を考慮すると、その値段は1500万円を大きく超え、2000万円台からスタートする可能性が高いと見られています。
まず参考になるのが、2025年8月に生産を終了したR35型GT-Rの最終モデルの価格です。標準グレードにあたる「Pure edition」ですら約1444万円、高性能モデルの「NISMO Special edition」に至っては、新車価格が3000万円を超えていました。この時点で、次期モデルがこれを下回る価格で登場することは考えにくいと言えます。
さらに、R36は単なるモデルチェンジではなく、クルマの根幹から変わる大きな進化を遂げます。1000馬力級の新たな電動パワートレインや、実用化されれば画期的となる全固体電池、カーボン素材を多用した軽量なエアロボディ、進化した4WDシステム「e-4ORCE」など、開発にも製造にも莫大なコストがかかる最新技術が惜しみなく投入される見込みです。
これらの理由から、R36はR35が持っていた「コストパフォーマンスに優れたスーパーカー」という立ち位置から、世界のライバルと肩を並べるプレミアム・スーパーカーへと完全に移行すると考えられます。もしR36にもNISMOや特別な限定モデルが用意されるとすれば、その価格は3000万円、あるいはそれ以上になることも十分にあり得るでしょう。
| モデル | 参考価格帯 |
|---|---|
| GT-R R35(2025年モデル Pure edition) | 約1,444万円~ |
| GT-R R35(2025年モデル NISMO) | 約3,008万円~ |
| 次期 GT-R R36(ベースモデル) | 1,600万円 ~ 2,000万円(予想) |
| 次期 GT-R R36(NISMOモデル) | 3,000万円~(予想) |
GT-RはNSXやLFAより速い?
日本の自動車史が生んだスーパーカーの最高峰として、NISSAN GT-R、ホンダ NSX、そしてレクサス LFAの3台は、常に比較対象としてその速さが議論されてきました。これまでのR35型GT-Rは、サーキットや条件によってNSXやLFAとしのぎを削る速さを見せてきましたが、R36の登場はその勢力図を完全に塗り替える可能性があります。
R35 GT-Rの強みは、VR38DETTツインターボエンジンが生み出す圧倒的なパワーと、それを確実に路面に伝える独立型トランスアクスル4WDシステムにありました。
特に0-100km/hといった加速性能では、ミッドシップレイアウトのNSXやFRのLFAに対して優位に立つ場面が多く見られました。ニュルブルクリンク北コースのラップタイムを見ても、GT-R NISMOが記録した7分8秒679というタイムは、LFAのニュルブルクリンク・パッケージ(7分14秒64)をも上回る、国産市販車最速の記録です。
そして、次期モデルR36が1000馬力超の電動パワートレインを搭載した場合、その速さは新たな次元に突入します。モーターは、回転を始めた瞬間から最大トルクを発生できる特性を持つため、静止状態からの加速、いわゆる「ゼロ発進」はガソリンエンジン車の比ではありません。
R36の0-100km/h加速は、2秒台前半に達するとも言われ、そうなればNSXやLFAを過去のものにするほどのパフォーマンスを発揮するでしょう。
もはやR36のライバルは国産車の中に留まらず、世界のハイパーEVと競う存在となります。日本の技術の粋を集めた次世代GT-Rが、世界の頂点でどのような走りを見せるのか、期待は高まるばかりです。
伝統と革新、R36への期待

ここまで、次期GT-R R36のデザイン、開発状況、そして予想されるスペックや価格について見てきました。一部で囁かれる「GT-R R36はダサい」という評価は、未来的なコンセプトカーのデザインに対する戸惑いの声かもしれませんが、そのデザインは性能を極限まで追求した結果であり、GT-Rの魂である丸目テールといった「伝統」もしっかりと受け継がれる見込みです。
開発中止の噂も払拭され、日産がGT-Rというブランドの火を消すことなく、次世代へと繋ごうとしていることは明らかです。登場は2028年頃とまだ先ですが、その中身は私たちの期待を大きく超えるものになりそうです。
価格は2000万円を超えるプレミアムな領域に達するかもしれませんが、それは全固体電池や1000馬力超の電動パワートレインといった「革新」の証です。その圧倒的なパフォーマンスは、かつてのライバルを凌駕し、世界の頂点を狙えるポテンシャルを秘めています。
R36は、日本の自動車メーカーが誇る技術力の結晶として、GT-Rが築き上げてきた輝かしい歴史を受け継ぎながら、電動化という未来へ果敢に挑戦する一台となるでしょう。伝統と革新を融合させた、新たな時代の日本のスーパーカーの誕生を、世界中のファンが心待ちにしています。
GT-R R36がダサいという噂を総括
次期「GT-R R36」にダサいとの声もありますが、開発は継続中です。デザインは性能を追求した結果で、丸目テールといった伝統も継承します。1000馬力超のスペックで2028年頃の登場が待たれる、伝統と革新を融合した次世代スーパーカーです。
記事のポイントをまとめます。
- 次期デザインの基盤はコンセプトカー「ハイパーフォース」である
- デザインは見た目より空力性能を最優先した機能的なものだ
- 象徴的な丸目4灯テールは次期モデルでも継承される見込み
- R35後期のデザインは過去のスカイラインGT-Rへの敬意を示している
- レースでの活躍やメディア露出が世界的な人気の理由だ
- R35は誰もが楽しめる「マルチパフォーマンス」がコンセプトである
- 性能を追求した結果、R35には視界が悪いという欠点があった
- 開発中止は誤解であり、日産は次期モデルの開発を継続中だ
- R35の生産終了は部品調達難や法規制への対応が理由である
- 次期モデルR36の発売は2028年頃が有力視されている
- 発売時期は「全固体電池」の実用化ロードマップと関連する
- 次期モデルは電動化され、出力は1000馬力超と予想される
- 0-100km/h加速は2秒台前半に達し、ライバルを凌駕する見込み
- 新車価格は1500万円を超え、2000万円台からと予測される
- 伝統と革新を融合した次世代スーパーカーの誕生が待たれる